

プロアクティブセキュリティ:露出管理と検知・対応能力の役割
サイバー攻撃の高度化と常態化が進むなか、「検知と対応」を中心としたセキュリティの考え方では、もはや被害の発生を十分に防ぎきれない状況が生まれつつあります。こうした現状を踏まえ、攻撃が発生する前の段階からリスクを把握し、先手を打つ取り組みの必要性が高まっています。

本稿では、「Operation Secure」と呼ばれる多国間の法執行機関による取り組みについてご紹介します。この作戦では、アジア太平洋地域で広く拡散していた情報窃取型マルウェアのインフラを解体することに成功しました。トレンドマイクロは、本作戦において中核的な役割を果たし、脅威インテリジェンスの提供を通じて摘発の実現に貢献しました。


サイバー攻撃の高度化と常態化が進むなか、「検知と対応」を中心としたセキュリティの考え方では、もはや被害の発生を十分に防ぎきれない状況が生まれつつあります。こうした現状を踏まえ、攻撃が発生する前の段階からリスクを把握し、先手を打つ取り組みの必要性が高まっています。


昨年1年間に確認した日本国内における「標的型攻撃」に関しての分析によれば、APTとも呼ばれる高度な標的型攻撃が変化を続けながら継続して確認されています。


トレンドマイクロは、AIインフラを狙った攻撃に関するケーススタディを「MITRE ATLAS」に提供しました。本ケーススタディは、組織のサイバーレジリエンス強化に貢献します。


トレンドマイクロは、エージェント型AIとデジタルツインを組み合わせ、サイバー脅威に対する組織の防御を根本から変革する新たな運用モデルを提案しています。


金融庁の発表によると、2025年1月から5月末までの期間における証券口座への不正アクセス件数は10,422件、不正取引件数は5,958件、不正売買額は5,240億円に達し、被害が拡大しています。
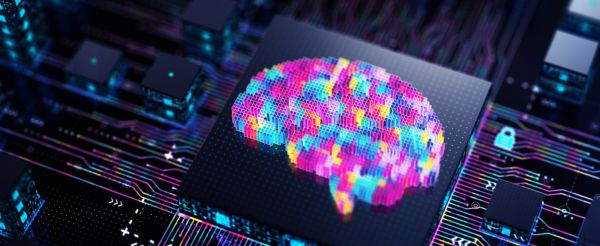
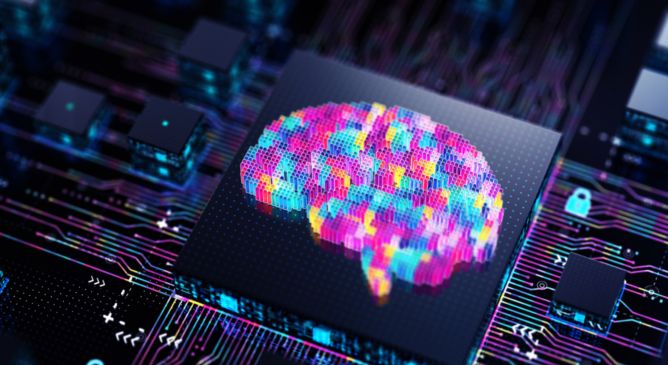
初のプロアクティブ型サイバーセキュリティAIであるTrend Cybertron が、NVIDIAの新しいユニバーサルLLM NIMマイクロサービスの力をどのように活用してAI for Securityを加速しているかをご紹介します。


セキュリティ回避やサプライチェーン攻撃の手段として蔓延しつつある「レジデンシャルプロキシ」について、犯罪ビジネスにおける立ち位置や技術詳細を中心に解説します。


AIエージェントに関する連載の締めくくりとして、コード実行、データ送出、データベースアクセスなどの領域におけるプロアクティブなセキュリティ対策を中心に考察します。


本稿ではSQL生成の脆弱性、保存されたプロンプトインジェクション、ベクターストアの汚染といった手法が、攻撃者によって詐欺行為に利用される可能性について分析します。


Trend™ Researchが追跡する中国背景の標的型攻撃グループ「Earth Lamia」は2023年以降ブラジル、インド、東南アジア諸国の複数業界へWebアプリの脆弱性を悪用した攻撃活動を活発化させています。