

2024年は中国、ロシア、北朝鮮のAPTグループによる攻撃を観測~標的型攻撃の最新動向~
2024年に観測した日本の国内組織や台湾をはじめとした日本周辺国への標的型攻撃の動向について、トレンドマイクロによる独自リサーチを踏まえて解説します。
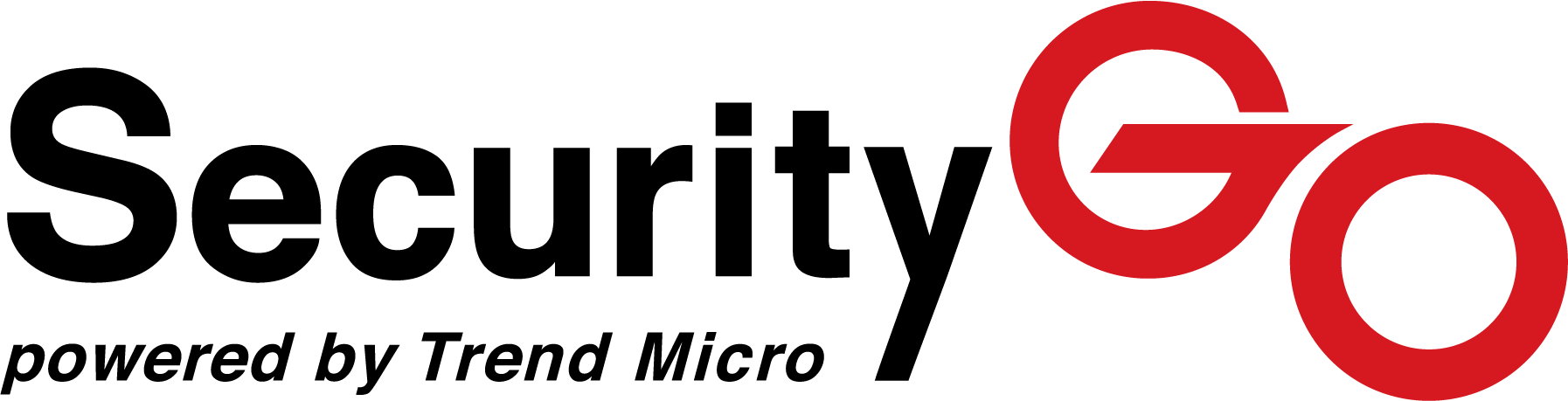

当社主催のサイバーセキュリティカンファレンス、「Trend World Tour 25」。8月1日東京、8月29日大阪で開催される本イベントの見どころをご紹介します。


2024年に観測した日本の国内組織や台湾をはじめとした日本周辺国への標的型攻撃の動向について、トレンドマイクロによる独自リサーチを踏まえて解説します。


情報漏洩発生要因の大きな原因である、従業員による内部不正による被害は常に報告され続けています。ほぼすべての業務情報がデジタル化し、可搬性も向上した現代。いかに内部不正から情報を保護するかを考察します。


集団や組織における特定の目標を達成するために必要な能力を高める方法である「キャパシティビルディング」。スパイウェアや脆弱性情報の管理を題材に、サイバーセキュリティとの関係性を紐解きます。


当社主催のサイバーセキュリティカンファレンス、「Trend World Tour 25」。8月1日東京、8月29日大阪で開催される本イベントの見どころをご紹介します。


耐久性、可用性、スケーラビリティ、低コストを謳うAmazon S3。S3自体が提供する暗号化機能を悪用し、マルウェアも脆弱性も使用しないランサム攻撃が観測されました。その手口を解説し、対策を考えます。


サイバーセキュリティの分野でおなじみのMITRE ATT&CKを基盤とし、人工知能や機械学習システムに対する攻撃者のTTPをまとめたナレッジベース「MITRE ATLAS」について解説します。この記事は第3回です。


アメリカで、2022年に制定された「サイバーインシデント報告に関する重要インフラ法(CIRCIA)」。今回はその概要と各国の制度との違いを解説します。


サイバーセキュリティの分野でおなじみのMITRE ATT&CKを基盤とし、人工知能や機械学習システムに対する攻撃者のTTPをまとめたナレッジベース「MITRE ATLAS」について解説します。


2025年5月末、警察庁はインド共和国・中央捜査局(CBI)との共同調査で、日本人を標的にしていたサポート詐欺に関わった6人の被疑者を検挙したと発表しました。本稿ではサポート詐欺について、様々な法人組織での被害内容を紹介し組織が行うべき対策について記載します。


2025年5月14日、金融庁が大手・地方銀行に対し、耐量子暗号を活用したサイバー防御に着手するよう要請したと報じられました。来るべき量子コンピュータ時代に備え、NISTが標準化を進める耐量子暗号について解説します。