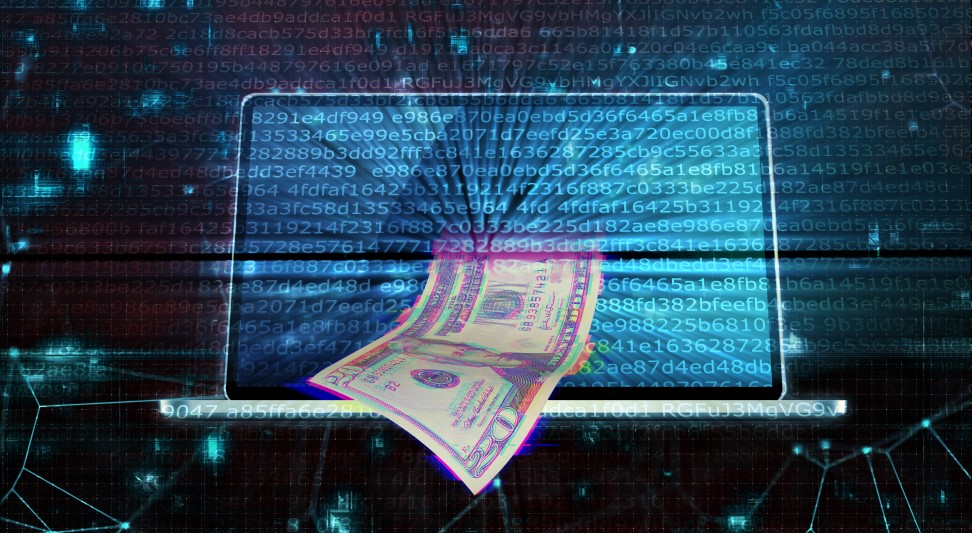安心=安全×信頼:2030年のセキュリティ社会4つのシナリオ
複雑なデジタル社会に生きる私たちにとっての「安心」を形成している要素とは?本稿では、安全学の観点から4つのセキュリティシナリオについて思考実験を行い、「安心」の未来について予想します。

論点:デジタル社会の「安心」を形成しているものは何か?
人間は、安心を求め、安全と信頼の社会で生きています。少なくとも、安心できる世の中で生きたいと望んでいることは間違いありません。人間が誕生してから今までの営みの多くは、脅威を退け、予見可能な未来の範囲を広げ、安心して生きられる世界を創り上げるための試みでした。2025年-。現在のデジタル社会に生きる私たちにとっても、それは変わりません。しかし、デジタル社会に生きる私たちにとっての「安心」を形成しているものは何なのでしょうか。本稿では、この難問に立ち向かいたいと思います。
セキュリティの真の目的は、安心の追求です。私たちはサイバーセキュリティに携わる身として日々、「デジタル社会における安心」について考え続けていますが、今やこの問題は技術的側面だけでなく、社会学的、哲学的、心理学的側面を含む複合的な課題となっています。とりわけ、AIという革命的な要素の登場と浸透により、2030年という近未来においても、私たちを取り巻く「安心」の形は現在とは異なる様相を呈すると予想されます。セキュリティの未来を考える上で、改めて私たちは「安心」という概念に立ち戻る必要があるのです。
本稿では、セキュリティの本懐である「安心」を、安全学※の視点から定義します。次に、産業革命によって変容してきた安全と信頼の関係性を整理し、いかにしてテクノロジーが安心の概念に影響を与えてきたかを概観します。そして、2030年の社会の可能性を「安心」の観点から4パターンに分け、そのシナリオを分析します。
※安全学:各々の分野の安全に共通する部分を、理念の下で技術・人間・組織の側面から統一的・総合的・体系的に考察する学問のこと。1990年代終わりに、科学史家の村上陽一 郎氏によって提唱された。
目的は、私たちが目指すべき未来への道筋を探ることです。一見すると抽象的で捉えどころのない「安心」という概念を、具体的かつ実用的な枠組みの中で捉え直すことで、デジタル社会における新たな「安心」の構築と議論の促進に貢献できれば幸いです。
安心=安全 x 信頼
「安心」という概念を包括的に理解するには、その複合的な性質を認識する必要があります。安全学(Safenology)の第一人者である向殿政男氏の先駆的な研究から得られる洞察として、安心は「安全」と「信頼」という2つの独立しつつも相互に関連する要素から構成されると考えることができます。まずは、「安全」と「信頼」の概念について概観してみましょう。
安全とは、国際標準化機構(ISO)や日本工業規格(JIS)において「許容不可能なリスクが存在しない状態」と定義される客観的な概念です。具体的には、「危害の発生確率」と「危害の深刻度」を組み合わせたリスクが、社会的・技術的に受容可能な水準に抑えられている状態を指します。例えば、機械設計においては、危険源※を特定し、リスク評価を行った上で対策を施し、残留リスクを許容範囲内に制御するプロセスが求められます。また、安全の核心は「絶対安全の不在」にあります。向殿氏が指摘するように、「安全とはリスクを経由して定義される」ため、この世の中に無リスク状態は存在しません。安全とは常に相対的であり、文脈依存であり、確率論的です。これはセキュリティひいてはリスクマネジメントを理解するうえで、極めて重要な前提です。
※危険源:JIS規格では、危害を引き起こす潜在的根源としている。
一方で信頼は、人々が自分の環境や使用する技術について自信を持つことができる主観的な感覚です。より学術的に言えば、不確実性を内在させた状態で発動する「他者の善意への期待」およびその関係性構築プロセスである、とも言えるでしょう。社会システム論的には、信頼を「リスクを承知で他者に依存する意思決定」と位置付け、情報非対称性下での協働を可能にする社会資本として機能します。
上記の定義をもって「安心=安全×信頼」を数学的に理解する場合、安全または信頼のいずれかがゼロに近づくと、もう一方が強力であってもセキュリティ全体が事実上崩壊するという重要な洞察が得られます。加えて、「安全責任は複数の利害関係者間で分担される」という認識も大切です。安全責任は誰か一人に委ねられるシーンというのはほとんどなく、使用者側や規制を課す国家側にも共有されるものです。現代におけるエコシステムはテクノロジーによるシステムの複雑化が進んでいるため、この視点がさらに重要になります。セキュリティとは技術開発者、ユーザ、規制当局、およびその他の利害関係者による共同作業から生まれるものです。
「安心=安全×信頼」という枠組みは、産業革命ごとの安全機構や信頼構造の変化を評価し、その歴史的進化から2030年へ向けた未来予測まで見通すための貴重な視点となります。
| 産業革命 | 時期 | 主な技術 | セキュリティ状況 | 安全機構 | 信頼構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1次 | 18世紀後半 | 機械化・蒸気機関・水力 | 工場や製造施設の物理的保護 | 初歩的な機械制御・工場規制 | 個人的関係・地域コミュニティによる信頼 |
| 第2次 | 19世紀後半~20世紀初頭 | 大量生産・電力・組立ライン | 労働者保護・工業施設保護 | 初期標準化・安全規制・検査プロセス | 制度上の信頼・職業資格・企業評判 |
| 第3次 | 20世紀中頃 | オートメーション・コンピューター・電子機器 | 情報セキュリティ開始・物理安全システム | 電子安全システム・初期サイバーセキュリティ対策・体系化されたリスク評価 | システムベース信頼・技術認証・ブランド評判 |
| 第4次 | 21世紀初頭~ | サイバーフィジカルシステム・IoT・AI・ビッグデータ | サイバーフィジカル統合型セキュリティ・データ保護 | アルゴリズムによる安全制御・予測型リスク分析・自動化されたセキュリティ対応策 | デジタル信頼フレームワーク・オンライン評判システム・透明性メカニズム |
| 第5次 | 2020年代以降~現在 | 人間と機械協働型技術・持続可能技術・価値駆動型システム | デジタル/物理/社会領域統合型セキュリティ | 適応型安全システム・AI補強型リスク検知・人間中心設計 | 倫理フレームワーク・説明責任制度・参加型ガバナンス |
第1次産業革命:機械化による物理的保護
第1次産業革命(18世紀後半)は、人類初めて手作業から機械化製造へ移行した時期でした。この時代には主として工場や製造施設など価値ある資産や設備そのものへの物理保護が求められていました。安全機構としての方法論は非常に初歩的であり、多くの場合、大規模故障防止のみならず労働者保護まで考慮されていなかった、と言えるでしょう。現代では常識となっている「職場安全」という概念自体もほぼ存在せず、多くの鉱山や製造現場では、数多くの危険が存在し、それに対する安全対策はほとんど講じられていませんでした。
この時代における信頼構造は、主に個人的な関係や地域コミュニティに基づいていました。デジタルインフラが存在しなかったため、セキュリティに関する関係性は直接的で目に見えるものでした。複雑な技術的仲介が存在しない分、信頼は人間同士の関係性や地域社会のつながりに依存していたと言えるでしょう。
第2次産業革命:安全の制度化
第2次産業革命(19世紀後半から20世紀初頭)は、大量生産と組立ライン、そして電力による製造プロセスの劇的な変化をもたらしました。労働者保護や工業施設の安全が重要視されるようになり、安全性に関する考え方が徐々に制度化されていった時代です。労働運動が勢いを増し、労働条件の改善や規制強化が求められる中で、安全規制や検査プロセスが整備され始めました。また、この時代にはパンチカードシステムなど初期的なコンピューター技術が業務に導入され始めましたが、ネットワーク接続がないため、サイバーセキュリティという概念はまだ存在していませんでした。
信頼構造は、個人的なものから制度的なものへと進化しました。職業資格や公式な検査プロセスが信頼を担保する役割を果たすようになり、工業規模の拡大に伴い、個人間の直接的な関係性だけではなく、組織的・制度的な信頼が求められるようになりました。
第3次産業革命:デジタルセキュリティの夜明け
第3次産業革命(20世紀中頃)は、自動化やコンピューター技術、電子機器によって製造プロセスがさらに高度化された時代です。この時期には情報セキュリティという分野が初めて独立した学問・実務領域として認識されるようになりました。製造プロセスがコンピューター化されるにつれ、新たな課題として浮上したのが「情報の整合性確保」です。その社会的要請を受けて、電子安全システムが登場し、人間だけでなく機械やシステム自体を守るための高度な保護手段が開発されました。また、ネットワーク化されたシステムが徐々に普及する中で、初期的なサイバーセキュリティ対策も導入され始めました。ただし、この時点ではまだ多くの場合、組織や業界ごとに閉じた形で運用されていたという点が現代との大きな違いです。
信頼構造はさらに進化し、システムベースのアプローチへと移行しました。技術認証や標準化されたガバナンスフレームワークが信頼を担保する役割を果たすようになり、ブランドの評判も重要性を増しました。消費者と生産者との直接的なつながりが減少する中で、標準化された認証やブランド力による信頼形成が求められるようになったのです。
参考記事:
・ISMSとプライバシーマークは何が違う? 概要や違いを解説
・PCI DSSとは? クレジット産業向けのデータセキュリティ基準を解説
・FedRAMPとは?~制度の概要と認証までのプロセスを解説~
・ISMAPとは?クラウドサービスリストへの登録のメリットは?
第4次産業革命:セキュリティの融合
現在進行中である第4次産業革命(21世紀初頭~)は、サイバーフィジカルシステム(CPS)、IoT(モノのインターネット)、人工知能(AI)、ビッグデータ分析などによって特徴づけられています。この時代にはサイバーセキュリティと物理的安全性との統合が進み、「サイバーフィジカルセキュリティ」という新しい概念が登場しました。例えば、自動運転車やスマートホームなどでは、物理的な安全性とデジタルシステムの安定性が一体となって機能する必要があります。この時代には、防御的な姿勢から脱却し、予測分析や自動応答などを活用したより予測的なアプローチへと進化しています。サイバーセキュリティと物理的安全性との境界線は曖昧になりつつあり、デジタルシステムはますます重要なインフラを管理する役割を担うようになっています。一方で、「急速なデジタル変革によるセキュリティへの影響」は新たな課題として浮上しています。
信頼構造も大きく変化しました。オンライン評判システムや透明性メカニズムなど、新しい形態の信頼構造が登場しています。しかし同時にプライバシーやデータ保護、アルゴリズムバイアスへの懸念も増大しており、新たな信頼課題も生まれています。誤情報や情報処理のブラックボックス化などの「AI技術の浸透による副作用」も顕在化しています。
参考記事:
・ディープフェイクとは
・フェイクニュースの影響について事例を交えて解説
・フィルターバブルとは? 意味と危険性をわかりやすく解説
・AIの発展とその影響:2024年の世界の動向まとめ
第5次産業革命:全体論的セキュリティへ
現在進行中でありつつも未来志向である第5次産業革命(2020年代後半以降)は、人間と機械との協働技術および持続可能技術システムに焦点を当てています。このパラダイムでは純粋な効率性から目的志向型イノベーションへの移行を象徴しており、安全性と倫理性を統合した全体論的セキュリティへの移行を目指しています。安全アプローチはより適応型かつ文脈依存型となりつつあり、AI技術による補強型リスク検知技術を活用しながら、人間中心の設計原則を重視しています。「倫理設計」や「バリューセンシティブな設計(Value-Sensitive Design)」の導入によって、安全性は社会的・倫理的配慮なしには語れないものとして再定義されています。
信頼構造も参加型モデルへと進化しています。倫理フレームワークや説明責任制度、透明性ガバナンスなどが技術開発の基盤となりつつあります。国連開発計画(UNDP)が指摘するように、「人々の安全と包摂に焦点を当てた予防的かつ適応型措置」への移行が急務となっています。
この歴史的進化を見ると、安全機構と信頼構造という2つの要素がどのように変容してきたか理解できるだけでなく、それらの統合によって2030年以降の未来像をどのように描くべきかについても洞察を得ることができます。
参考記事:
・AIガバナンスの動向は?各国のAI法規制を概観
・AIアクション・サミット:世界のリーダーが革新、規制、セキュリティを議論
・AI TRiSM(エーアイトリズム)とは何か?~AI時代に必要なフレームワーク~
・AI進化の先にあるのは善か悪か?~2024年の“デジタルジレンマ”を読み解く
2030年における「安心社会」の4シナリオ
2030年までにはAIシステムがおそらく社会インフラとして不可欠な存在となり、医療提供からエネルギー管理、交通ネットワークから金融システムまであらゆる分野で統合されているでしょう。この文脈で私たちの「安心」の概念はどのように進化するのでしょうか?この問いに答えるため、「安全」(客観的条件としてのリスク軽減)と「信頼性」(主観的認識としての信頼)の2つの重要な軸を基に、4つの異なるシナリオを考案しました。これらのシナリオは予測ではなく、2030年におけるセキュリティのさまざまな可能性を探るための仮説的な未来像です。思考実験とそれに付随する議論の活性化のため、各シナリオにおける特徴が最大化された社会を表現しています。
| 信頼性/安全 | 安全である | 安全でない |
| 信頼できる | シナリオ1:協調型 | シナリオ3:幻想型 |
| 信頼できる | シナリオ2:パターナリズム型 | シナリオ4:ディストピア型 |
表:「安全×信頼」基準に基づくセキュリティ社会の4パターン
シナリオ1:安全かつ信頼できる世界 —「協調型セキュリティ社会」

『強調型セキュリティ社会』では、堅牢な技術的安全保障が強力な倫理フレームワークや透明性のあるガバナンスと調和し、客観的に安全で主観的にも信頼される技術環境が実現しています。2030年までに、AIシステムの開発は厳格な安全基準と包括的なガバナンスプロセスによって導かれ、人間の幸福が技術的性能と同等に重視されています。国際標準化機関はAI安全性に関する明確なベンチマークを設定し、学際的な監視機関がこれらの基準を新興技術に合わせて進化させています。
この世界におけるセキュリティの特徴は以下の通りです:
・予防的リスクマネジメント:高度な分析技術が潜在的な脆弱性を事前に特定し、セクターや国境を越えた協調型セキュリティオペレーションセンターが脅威インテリジェンスを共有します。
・透明性のあるガバナンス:AI開発と展開に関する意思決定プロセスが可視化され、失敗や被害が発生した場合には明確な説明責任メカニズムが存在します。
・参加型設計:多様な視点を取り入れたセキュリティアーキテクチャが構築され、特定コミュニティだけでなく幅広い社会層のニーズに応える設計が実現します。
・強靭なインフラ:重要インフラは複数の冗長性やレジリエンスを備え、攻撃を受けても基本機能を維持できるよう設計されています。
このシナリオでは、セキュリティは単なる技術的特性ではなく、協調によって達成されるものと理解されています。多くのサイバーセキュリティ専門家が認識しているように、「デジタルセキュリティ分野で最大の脅威は技術的というよりもむしろ人間的である」という認識が、このシナリオでは両面から対処されています。
シナリオ2:安全だが信頼できない世界 —「パターナリズム型セキュリティ社会」

技術的パターナリズムが権力を持つ社会では、技術システムは包括的な監視と制御メカニズムによって驚異的な安全水準を達成していますが、プライバシーや自律性への懸念から公共の信頼性は低下しています。2030年までに、重要インフラを含めた多くのシステムがかつてないほど高い信頼性で稼働しており、AI駆動型セキュリティシステムは従来型サイバー攻撃によるインシデント数を劇的に減少させます。しかし、この技術的成功には大きな社会的コストを強いている点が、この社会の最も顕著で悲劇的な特徴です。
この世界におけるセキュリティの特徴は以下の通りです:
・全方位監視:至る所に配置されたセンシング技術と予測分析によって潜在的脅威を事前に特定しますが、それと同時に包括的な監視ネットワークが構築され、人間活動のほぼすべてが追跡されています。
・非対称な透明性:企業や政府は市民やユーザから包括的データ収集を要求する一方で、自らの運用やデータ利用方法についてほとんど情報公開しません。
・テクノロジー・パターナリズム:システムはユーザ代わりにセキュリティ判断を自動で行い、安全指標優先で個人選択や文脈依存性を軽視します。
・集中管理:重要インフラ管理権限は政府または企業など少数機関に集中しており、その結果として失敗や悪用時には単一障害点(Single Point of Failure)が生じます。
この世界では、安全性という概念が「リスク管理」よりも「リスク排除」として主に定義されており、制約重視型アプローチへ傾倒しています。安全学においては「安全基準策定時には一定程度のリスク許容余地も必要」であるにもかかわらず、このシナリオではその原則がほぼ放棄されています。このシナリオにおける皮肉は、「何も悪いことが起きない」ほど安全なシステムを構築する過程で、プライバシー侵害や人間主体性の喪失という新たな社会問題を生み出してしまっている点です。
シナリオ3:信頼できるが安全でない世界 —「幻想型セキュリティ社会」

このシナリオでは、優れたUX(ユーザエクスペリエンス)設計と、情報の非対称性を逆手に取ったマーケティングメッセージによって、ユーザ側に強い安心感(信頼)が醸成されている状態です。一方で、未検証コードの大量投入や不十分な検査体制が放置され、システム上の根本的脆弱性(=安全の欠如)が放置され続けています。このような状況では、セキュリティシステムが見かけ上は正常に動作しているように見えても、実際には基盤となる設計や実装に深刻な脆弱性が潜んでいます。これにより、攻撃者がその脆弱性を悪用し、重大な被害を引き起こすリスクが高まります。このようなギャップは非常に危険です。
この世界におけるセキュリティの特徴は以下の通りです:
・セキュリティ・シアター(見せかけの安全)
表面的な対策(例:派手な認証アニメーションや過剰な警告メッセージ)にリソースが集中し、根本的な脆弱性が放置されます。ユーザは「複雑な手続き=安全」と錯覚し、実際のリスクを見落とす傾向があります。
・学習の先送り
重大なセキュリティ事故が発生しても「特殊な事例」として片付けられ、根本原因の解消が先送りされます。例えば、医療機関での個人情報漏洩が相次いでも、「人為的ミス」の一言で済まされ、システム全体の再設計が行われません。この「パッチワーク型対策」は問題を慢性化させます。
・信頼の悪用
ユーザの安心感を利用し、過剰なデータ収集や不要な権限要求が横行します。例えば、フィットネスアプリが「健康管理のため」と称して位置情報や生体データを収集し、第三者が悪用する事例が多発します。ユーザは「信頼できる企業なら大丈夫」という思い込みから、リスクを過小評価します。
・脆弱なシステム基盤
迅速なサービス展開を優先し、基幹システムのテストが不十分なままリリースされます。AI生成コードの未検証状態での流用や、オープンソースライブラリの管理ミスが典型例です。一見正常に動作していても、特定の条件下で致命的な脆弱性が顕在化する「時限爆弾型リスク」を内包しています。
・分断された責任体制
開発部門・運用部門・経営陣間で責任のたらい回しが発生します。クラウドサービス障害が起きた際、ベンダーは「ユーザの設定ミス」、ユーザ組織側は「ベンダーの設計不備」と主張し合い、根本的な課題解決が進みません。
これらの特徴は、技術的脆弱性と社会的認知の乖離によって生じる「安心感の罠」を浮き彫りにします。ユーザが感じる安心感と実際の安全性のギャップが拡大するほど、いざ重大事故が発生した際の社会的ダメージは深刻化します。皮肉にも、このシナリオの世界では「安心感」が過剰に優先される結果として、「安全性」が犠牲になっています。これはまるで、豪華で美しい外観を持つ家が、実際には紙で作られているようなものです。一見すると堅牢で信頼できるように見えるシステムも、その基盤が脆弱であれば一瞬で崩壊する危険性があります。
シナリオ4:安全も信頼もない世界 —「ディストピア型セキュリティ社会」

このシナリオでは、安全性と信頼性の両方が欠如しており、不安定で混乱した環境が広がっています。技術的な脆弱性と公共の不信感が相互に作用し、セキュリティ対策は効果を失い、多くの人々や組織にとって危険な状況となります。セキュリティに対する学習性無力感が社会に充満している状態です。2030年までに、多くの深刻なセキュリティインシデントが発生し、それによって政府や企業への信頼が失墜します。一方で、技術革新への過剰な競争圧力や資源不足によって、セキュリティ検証プロセスの省略や無考慮などにより、基本的なセキュリティアーキテクチャの欠陥が放置されています。
この世界におけるセキュリティの特徴は以下の通りです:
・反応的姿勢:セキュリティ対策は主に事故発生後の対応に集中し、予防的アプローチはほとんど取られていません。
・分断されたガバナンス:規制や基準が地域ごとに異なるため、グローバルシステム間でセキュリティギャップが生じています。
・信頼崩壊:公共の信頼感は低下し、多くのユーザはどんなシステムも信用できないと考えています。その結果として、有効なセキュリティ対策さえ拒否されることがあります。
・セキュリティ格差:効果的なセキュリティ対策へのアクセスは資源豊富な組織や個人に限られ、多くの人々は脆弱な状態に置かれています。
このシナリオでは、安全性と信頼性という2つの要素が同時に低下することで、セキュリティ全体像が崩壊しています。「安全=安全×信頼」という公式は、この状況下でその重要性を痛感させます。どちらか一方でも欠ければセキュリティは成立しません。
皮肉にも、この世界では「セキュリティ対策」がむしろ混乱を助長しています。「絶対的な安全は無い」という事実が、戦略の「前提」ではなく「結果」として捉えられており、社会全体に「やっても無駄」という無力感が漂います。セキュリティへの投資は主に経済合理性によってのみ判断され、物理的・社会的・心理的被害が過小評価されています。
上記4つのシナリオに共通する点として、以下が挙げられます:
1. 技術的論点と社会的論点の不可分性:技術的安全保障と社会的信頼関係との相互作用がセキュリティ成果を決定づけます。
2. ガバナンスモデルの重要性:意思決定権限の分配方法が、安全性と信頼性双方へ大きく影響します。
3. 透明性による強靭化:対策の限界や脆弱性について正直に伝えることは、一見完璧そうに見せるよりも強固なセキュリティ構築につながります。民主的な議論を行うために、発信/受信側の双方に情報リテラシーが求められます。
4. セキュリティ格差による全体影響:保護手段への不平等アクセスは相互接続されたシステム全体へ波及します。
方法:何を考え何をすべきか
これまで産業革命を通じたセキュリティの進化を検討し、2030年に向けたセキュリティのシナリオを探ってきました。その結果、明確な結論が浮かび上がります。それは、これから直面するセキュリティの課題は、単なる技術的な手段だけでは解決できず、また狭い専門分野のアプローチだけでは不十分だということです。本当に安全で信頼できる未来を創るためには、「知性の融合」とも呼べるような、多様な視点や方法論、知識分野を結集させる必要があります。セキュリティを複雑な社会技術的課題として捉え、それに対応するための包括的なアプローチが求められるのです。
セキュリティへの学際的アプローチ
2030年に向けたセキュリティパラダイムを構築するには、従来の境界線を超えた学際的アプローチが必要です。これはサイバーセキュリティ内部だけでなく、政治、経済、環境、技術といった幅広い領域にまたがるものです。この学際的アプローチには以下のような利点があります:
1. 包括的なリスク評価
多様な分野からの視点を統合することで、技術的・社会的・組織的次元にまたがるセキュリティ脅威をより包括的に理解できます。例えば、「Cyber Security For Europe」の研究では、「社会心理学、行動経済学、教育学、ユーザ体験設計(UX)、フレーミング理論、コミュニケーション理論、および説得科学」といった多様な知見が効果的なサイバーセキュリティ意識向上には不可欠であるとされています。
2. 強靭な設計原則
学際的コラボレーションによって、人間行動や社会組織要因も考慮した安全設計アーキテクチャが開発されます。これにより、安全性は単なる技術システム内で完結せず、人間と技術との相互作用から生まれるものとして捉えられます。
3. 予測型ガバナンス
多様な専門知識を結集することで、新たなセキュリティ課題が危機として顕在化する前に予測し対処する能力が向上します。この前向きなガバナンスモデルでは、危機対応型ではなく予防型のリスクマネジメントが優先されます。
4. 信頼中心の開発
学際的アプローチによって、信頼という要素が技術開発ライフサイクル全体で考慮されるようになります。これにより、「機能性」が確立された後で「信頼性」を後付けするのではなく、その両者が同時並行で発展します。
このような学際的アプローチは、安全性と信頼性という2つの要素を統合し、本物のセキュリティを実現するために不可欠です。また、安全性とは人間の価値観や社会関係について考えることであり、それ自体が単なる技術保護策以上のものであることも忘れてはなりません。
2030年に向けて、私たちがセキュリティをどのように設計するかは、技術的卓越性だけでなく、倫理的ガバナンスや透明性のあるコミュニケーション、多様性を尊重した設計思想によって決まります。これらすべてが整合することで初めて、本当の意味で安全かつ信頼できる未来社会を構築できるでしょう。
本稿に一貫して採用してきた「安心=安全×信頼」という公式は私たちに重要な教訓を与えています。どれほど完璧な技術的安全対策でも、それに対応する信頼関係が欠如していればセキュリティは成立しません。また逆に、信頼だけでは安全性が伴わない場合、それは危険な錯覚となります。この両方を達成するには、多様な視点や知識体系を統合した包括的枠組みが不可欠です。
参考記事:
トレンドマイクロ製品の安全性・透明性向上のための5つ取り組み(全5回)
・第1回:製品開発の迅速性と安全性を両立するDevSecOps
・第2回:サービスの信頼性を確保するSRE(Site Reliability Engineering)の実践
・第3回:ソフトウェアの脆弱性のリスクを可視化するSBOM
・第4回:トレンドマイクロ製品の脆弱性に関する品質向上の取り組み
・第5回:地政学リスクを考慮した製品・サービスの設計とは
具体的には、単なる制約や管理ではなく、人々の能力や参加意欲を引き出すようなセキュリティアーキテクチャの設計が求められます。また、意思決定には民主主義的価値観と専門知識とのバランスが必要であり、安全保障は人間社会の繁栄と調和しながら機能すべきです。
最後に、「絶対安全は存在しない」という原則に立ち返ります。この基本原則は、セキュリティとは終着点ではなくプロセスそのものであり、絶えず適応し改善していく行動であることを教えてくれます。子供の成長を見守るように、結果ではなくプロセスに目を向けることが大切です。
私たちが今取り組むセキュリティの選択は、2030年の世界を深く形作るでしょう。学際的アプローチによる知性の融合を通じて、人間の創造性や尊厳を支える基盤としてのセキュリティを目指しましょう。
<関連記事>
・AIの発展とその影響:2024年の世界の動向まとめ
・AI進化の先にあるのは善か悪か?~2024年の“デジタルジレンマ”を読み解く
・「AIのリスク」に対する世界の取り組みを理解する(前編)~主要な組織編~
・「AIのリスク」に対する世界の取り組みを理解する(後編)~イニシアティブ・宣言編~
<参考文献>
・Safety Measures Should Assume People Will Make Mistakes and Machines Will Break Down (Daifuku, 2023)
・History of Workplace Safety (SafefyLine, 不明)
・Cybersecurity Futures 2030 New Foundations (World Economic Forum, 2023)
・In the Fourth Industrial Revolution era, Security, Safety, and Health (Chalaris, 2023)
・Closing the AI equity gap, Trust and safety for sustainable development (Massally & Louie, 2025)
・「信頼をつくるということ」―主体的信頼創造の可能性(浦田・佐藤・松枝, 2023)
・信頼研究序論(小川, 2020)
・第二回有識者コラム 安全と安心を考える(内田, 2009)
・バリューセンシティブなデザインとは何か VSDと技術哲学(北野, 2023)
・What is value-sensitive design? (TechTarget)
・信頼が生み出される社会を目指して(佐藤, 不明)
・安全における曖昧さと安全学(向殿, 2016)
・入門テキスト 安全学(向殿, 2016)
・セーフティ&セキュリティ入門: AI、IoT時代のシステム安全(金子, 2021)
・Multidisciplinary Approach in Cybersecurity Awareness(CyberSecurityForEurope, 2022)

Security GO新着記事
2025年の国内セキュリティインシデントを振り返る
(2025年12月11日)
サイバー攻撃の被害額から考えるセキュリティ
(2025年12月4日)
論考:ポストAgentic AI時代に必要なこととは?
(2025年11月20日)