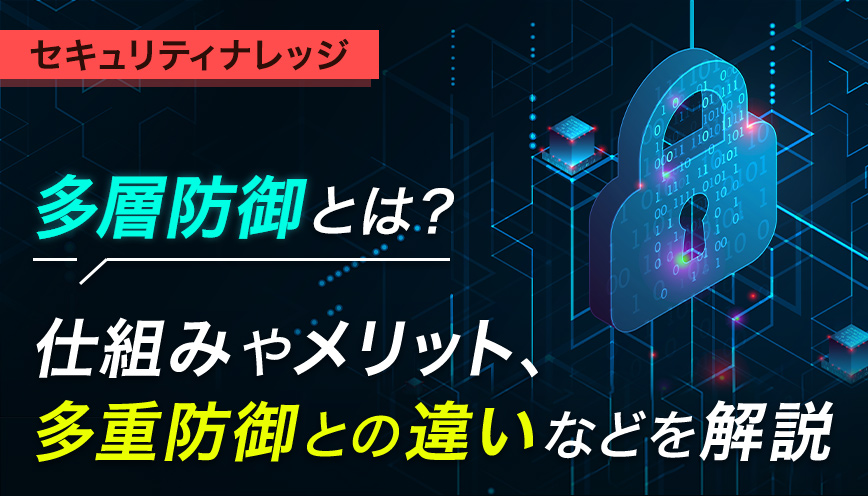企業に必要なセキュリティ対策とは?必要な理由や具体策などを解説
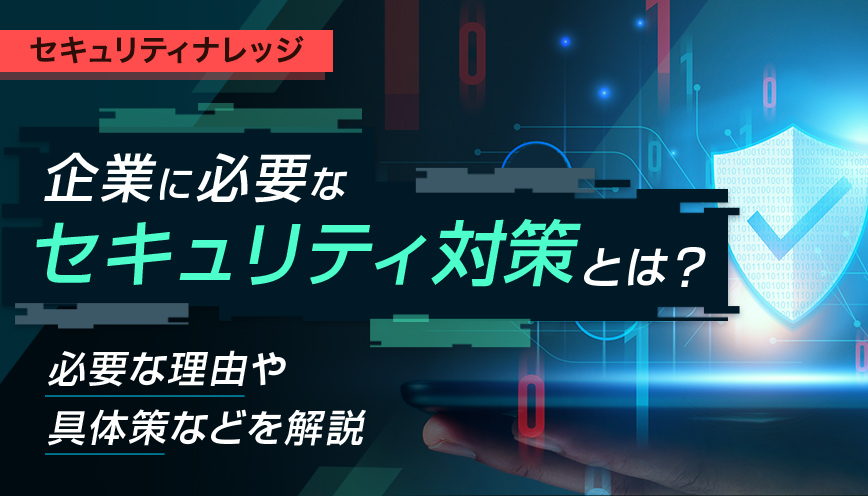
公開日
2023年9月29日
企業がビジネスを行う上で、セキュリティ対策は欠かせません。さまざまな業務でのクラウドサービスの利用が進む中で、サイバー攻撃の手口は日々、複雑化しているため、企業規模にかかわらず、しっかり備えておく必要があります。
この記事では、セキュリティ対策の目的や実施するべきセキュリティ対策、リスクごとの想定される被害と対策例、セキュリティ対策に効果的なシステムなどについて解説します。
セキュリティ対策はデジタル機器を安全に使用するための対策
セキュリティ対策は、ネットワーク通信やパソコンなどのデジタル機器を安全に使用するために必要な対応です。現代のビジネスにおいて、企業の機密情報や事業を行う上で必要な情報は、デジタルデータとして保管され、ネットワーク通信とパソコンなどのデジタル機器を使って管理・利用されています。
デジタルデータの活用によって、企業はさまざまなメリットを得られますが、一方で、ネットワーク通信を経由して外部からのサイバー攻撃を受けるリスクもあります。サイバー攻撃による情報漏洩などの事態を起こさないために、セキュリティ対策は、現代の企業にとって欠かせないリスク管理のひとつといえるでしょう。
また、クラウドサービスを利用する際は、よりいっそう緻密なセキュリティ対策がとなります。クラウドサービスは提供会社が一定のセキュリティ対策を講じていますが、利用する企業がセキュリティ対策を怠ると、不正アクセスを受けてしまう可能性もあります。クラウド上に保管している重要な情報が消失したり、流出したりすると、企業活動は深刻なダメージを受けてしまうため、企業はクラウド環境でのセキュリティ対策に取り組む必要があるのです。一方、クラウド環境は簡単に構築でき、簡単に公開できるという特性があるため、システム運用においては便利ではあるものの、セキュリティが不十分の状態で外部に公開されてしまうリスクも高くなります。
企業のセキュリティ対策の目的
サイバー攻撃の被害は大きなものになりやすく、時には事業存続できないほどのダメージをもたらす可能性もあるため、企業にとってセキュリティ対策が欠かせません。では、企業のセキュリティ対策は、具体的にはどのような目的で実施するのでしょうか。企業がセキュリティ対策を行う3つの目的について紹介します。
情報資産を守る
企業のセキュリティ対策の目的は、情報資産を守ることです。企業は、顧客の個人情報や取引先の情報、契約の情報、財務情報、人事情報、ソースコードなど、多くの情報を持っています。もしこれらの情報が流出すれば、顧客の信頼、取引先の信頼、市場での競争力などが失われ、事業に大きな影響を及ぼします。顧客や取引先に迷惑をかけることにもなり、顧客離れや取引停止が起きて、事業の存続が難しくなることもあります。
業務の継続
業務の継続も、企業のセキュリティ対策の目的のひとつです。サイバー攻撃などでシステム障害が起こると、復旧まで業務を中断せざるをえず、顧客へサービス提供できなくなるなど大きな影響が出てしまう可能性もあります。このような状況は、企業の信頼低下につながるだけでなく、補償対応が必要になる場合もあり、金銭的な損害も発生してしまうでしょう。
社会的信用を守る
社会的信用を守ることも、企業のセキュリティ対策の目的といえるでしょう。サイバー攻撃によって顧客や取引先の情報を流出させてしまったり、改ざんされたWebサイトを訪問した人がマルウェアに感染してしまったりすると、企業の社会的信用は失墜してしまうでしょう。
また、昨今では、大企業よりも比較的セキュリティレベルの低い中小企業を標的として不正にアクセスし、取引先の大企業へのサイバー攻撃の「踏み台」として利用する「サプライチェーン攻撃」も広がっています。このような手口に利用されてしまうと、経済的損失のみならず、企業イメージの毀損にもつながり、場合によっては事業の存続が難しくなってしまいます。
企業が実施するべきセキュリティ対策
企業はさまざまな目的からセキュリティ対策に取り組む必要があります。では、企業はどのような対策を講じるのがよいのでしょうか。多くの企業にも当てはまる、一般的な4つのセキュリティ対策を解説します。
ID・パスワードの管理徹底
企業が実施するべきセキュリティ対策は、ID・パスワードの管理徹底です。どんなに高性能なセキュリティ対策システムを導入しても、ID・パスワード自体が簡単に入手できたり、容易に推測できるものであったりするようでは意味がありません。ID・パスワードを厳重に管理するために、重要となる4つの要素を紹介します。
●容易に推測できるパスワードは使わない
ID・パスワードを厳重に管理するためには、容易に推測できるパスワードは使わないことが重要です。不正アクセスの手口の中には、IDとパスワードの組み合わせを大量に試して侵入を試みる「ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃)」により、不正ログインを行うものがあります。短いパスワードや容易に推測できるパスワード、「password」や「123456」などのよく使われるパスワードは不正アクセスにあいやすいので、長くて複雑なパスワードを設定しましょう。
●パスワードを使いまわさない
ID・パスワードを管理するときの注意点として、パスワードを使いまわさないということも周知するようにしましょう。不正アクセスの手口のひとつに、過去にどこかで流出したIDとパスワードのセットをほかの場所で試す「パスワードリスト攻撃」があります。そのため、パスワードを使いまわしていると、不正アクセスを受けるリスクが高まってしまいます。また、不正ログインされた際には、被害が拡大してしまうので、パスワードは複数用意すると良いでしょう。
●ID・パスワードを人目に付かないように管理する
ID・パスワードを管理する際、人目に付かないように管理することも有効です。紙媒体で保管するなら鍵のかかる場所、デジタルデータで保管するなら、安全性の高いパスワード付きの電子ファイルで保管するのがよいでしょう。
●信頼できるパスワード管理ツールやワンタイムパスワードの利用をする
信頼できるパスワード管理ツールやワンタイムパスワードを利用すれば、ID・パスワードの管理を厳重にできます。信頼できるパスワード管理ツールを導入すれば、パスワード管理の手間が軽減されるでしょう。また、一度きりのパスワードを発行して認証するワンタイムパスワードなら、有効時間が短く、一度だけしか使用できないので、安全性が高いといえます。
アップデートとバックアップ
アップデートとバックアップも、企業が実施するべきセキュリティ対策のひとつです。OSやソフトウェアは、開発元からセキュリティの脆弱性を修正するパッチや新しい脅威に対応する更新プログラムが配信されるので、リリースされたらできる限り早くアップデートしましょう。また、攻撃を受けた際にデータを復元できるように、日頃からこまめにバックアップを取っておくことも大切です。
脅威の把握とセキュリティ意識向上
脅威の把握とセキュリティ意識向上も、企業が実施するべきセキュリティ対策といえるでしょう。サイバー攻撃の手口は日々変化し、複雑化しているので、現在はどのような手口が多いのか知っておくことが大切です。例えば、「フィッシング詐欺が多い」と従業員に周知していれば、従業員がメールやWebサイトを見る際に警戒し、被害を避けられる可能性が高まります。
また、企業の場合は、従業員全員が気をつけなくては意味がないので、社内全体のセキュリティ意識を向上させることも大切です。外部のセキュリティ研修サービスなども活用し、定期的に研修などのセキュリティ教育を行いましょう。
セキュリティ対策システム導入
企業が実施するべきセキュリティ対策には、セキュリティ対策システムの導入も挙げられます。セキュリティ対策システムは、コンピュータウイルスへの感染や不正アクセスのリスクを下げるために有効です。メールを開く際やWebサイトを閲覧しているときに、自動でコンピュータウイルスを検知し警告してくれる、不正アクセスを検知しブロックしてくれるといった機能があります。また、導入後は必ず定期的にアップデートを行ってウイルス定義を更新すること、定期的にウイルススキャンを行うことが重要です。
リスクごとの想定される被害と対策例

さまざまな対策を通じて、企業はセキュリティ対策を実施することが可能です。一方、セキュリティ上のリスクにもさまざまな種類があります。ここでは主な4つのリスクについて、想定される被害と有効なセキュリティ対策を紹介します。
ウイルス感染
セキュリティに関する被害のひとつにウイルス感染があります。主な感染経路としては、メールの添付ファイルや悪意のあるWebサイトへのアクセス、ファイルのダウンロード、ソフトウェアの脆弱性をついての攻撃などがあります。コンピュータウイルスに感染すると、情報を抜き取られる、デバイスに保存されているデータが改ざんされる、デバイスを乗っ取られるといった被害にあう可能性があります。
対策としては、ウイルス対策ソフトを導入する、不審なメールや添付ファイルを不用意に開かない、不審なWebサイトを閲覧しない、OSやソフトウェアを最新の状態に保つといったことが大切です。
不正アクセス
企業のセキュリティリスクの被害として不正アクセスも挙げられるでしょう。不正アクセスには、アクセス権限を持たない第三者が、悪意を持ってサーバやシステムに侵入する行為のことで、何らかの方法で入手したID・パスワードを使って本人になりすます行為も含まれます。ID・パスワードの流出・盗難、システムの脆弱性からの侵入、コンピュータウイルスに感染させて侵入経路を確保してからの侵入などが主要な手口です。不正アクセスを受けると、データの流出や改ざん、サーバの停止、別企業へのサイバー攻撃の踏み台にされるといった可能性があります。
不正アクセスに対しては、ファイアウォールやIDS(不正侵入検知システム)・IPS(不正侵入防止システム)の導入、OSやソフトウェアを最新の状態に保つといった対策が有効です。
情報漏洩
情報漏洩の被害は、サイバー攻撃のほか、メールの誤送信など、従業員のヒューマンエラーでも発生してしまいます。情報漏洩が発生してしまった場合の被害には、顧客や取引先情報の流出による顧客からの信用失墜などが想定され、金銭的な補償が必要になる場合もあるでしょう。
対策としては、社内のガイドラインと作業ルールの策定やセキュリティ教育の徹底、データの共有設定の見直し、適切なパスワード設定などが効果的です。
機器の障害
停電や自然災害などによる機器の障害のひとつとしてサーバに問題が発生することが想定されます。具体的な被害には、復旧までのあいだ、データにアクセスできなくなる、データが消失してしまうといった可能性があります。
対策としては、定期的にバックアップを取る、データの保管場所を分散させておくなどがよいでしょう。また、サーバを設置する施設の耐震・耐火設備の整備も重要です。なお、機器の障害については、クラウドを利用することで、クラウド事業者が対応する責任範囲とすることができ、自社の対応範囲を削減できます。
セキュリティ対策に効果的なシステム
さまざまなセキュリティリスクを低減するため、企業にとってセキュリティ対策が欠かせません。特にシステムを導入すれば、効果的にセキュリティ対策を行うことができます。ここでは、代表的な4つのシステムを紹介します。
ファイアウォール
セキュリティ対策に効果的なシステムに、ファイアウォールがあります。ファイアウォールは、サーバの外側に設置して、インターネット側からサーバへの不要な通信を遮断したり、実際に行われた通信の記録を取ったりするツールです。IPアドレスやポート番号をもとにアクセスを制限します。
IDS(不正侵入検知システム)・IPS(不正侵入防止システム)
IDS(不正侵入検知システム)・IPS(不正侵入防止システム)も、セキュリティ対策に効果的なシステムといえるでしょう。IDSは、インターネットとの通信を監視して、不正アクセスや異常な通信を検知すると管理者に通知するシステムです。一方、IPS(不正侵入防止システム)は、不正アクセスを行おうとする動きを検知し、ブロックまで実施します。
WAF(Webアプリケーションファイアウォール)
WAFも、セキュリティ対策に効果的なシステムのひとつです。WAFはWebサイト上のアプリケーションに特化したファイアウォールです。Webアプリケーションの脆弱性を利用した不正アクセスから、アプリケーションを保護します。
総合セキュリティサービスを活用しよう
サイバー攻撃は非常に大きな被害をもたらす可能性があるため、どんな企業にとってもセキュリティ対策が必要不可欠といえます。ただ、サイバー攻撃の手口は日々巧妙になっており、自社のみでの適切な対応は難しいため、総合セキュリティサービスを利用するのがおすすめです。
トレンドマイクロのTrend Cloud Oneを活用すれば、効率的なセキュリティ対策が可能です。Trend Cloud Oneは、企業のセキュリティ対策に必要な機能を多く備えておりますので、ぜひご活用ください。
監修

福田 俊介
トレンドマイクロ株式会社 ビジネスマーケティング本部
ストラテジックマーケティンググループ
グループ長 シニアマネージャー
IPA 情報処理安全確保支援士(第000893号)、AWS Certified Solutions Architect – Professional保有。
約10年間クラウドセキュリティ領域およびエンドポイントセキュリティ領域に従事、クラウドの最新アーキテクチャに対応するセキュリティ戦略を立案、市場啓蒙を実施。これまでのセミナー登壇は100回を超える。専門領域は「クラウド」「サーバ」「仮想化」「コンテナ」「脆弱性」「EDR」「XDR」。
電子公告 | ご利用条件 | 個人情報保護方針 | Privacy and Legal |利用者情報の外部送信について | 製品使用許諾契約 |プレスリリース | サポート | サイトマップ | RSS
Copyright ©2026 Trend Micro Incorporated. All rights reserved